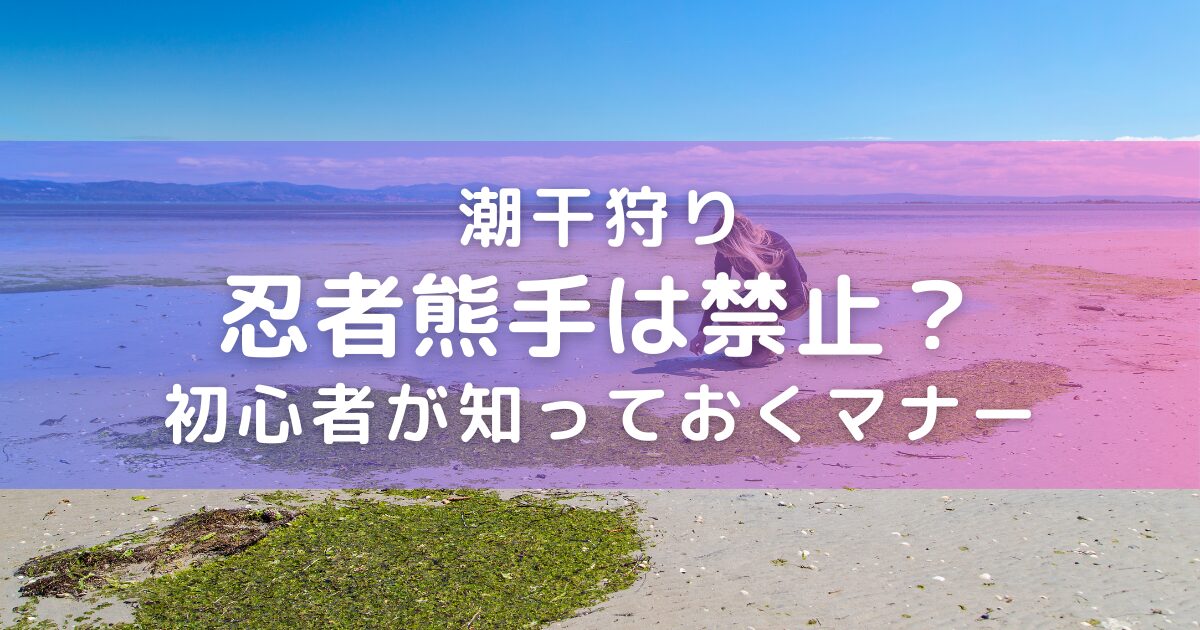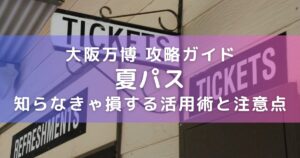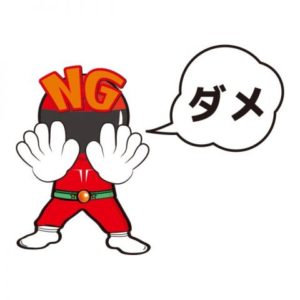春から初夏にかけて、日本各地で楽しめるレジャーといえば「潮干狩り」。海岸に出かけて貝を探すシンプルな体験ながら、大人も子どもも夢中になれる人気のアクティビティです。しかし、近年話題になっているのが「忍者熊手」の使用禁止。便利な道具がなぜダメなのか?ルールを知らずに使ってしまうと、楽しい潮干狩りが台無しになることも。本記事では、忍者熊手が禁止されている理由や、地域ごとのルール、マナー、そして自然と共に楽しむための心得まで、わかりやすく丁寧に解説します。
潮干狩りで使ってはいけない道具って?
忍者熊手って何?その特徴とは
潮干狩りのときに使われる「忍者熊手」は、見た目が普通の熊手と少し違います。主な特徴は、先端に鋭い金属製の爪がついていて、しかも長さがあったり、網がついていたりして、一度でたくさんの貝を効率よく掘れるようになっていることです。まるで忍者が使う秘密道具のような見た目から「忍者熊手」と呼ばれています。
しかしこの便利さが問題になっています。一般的な熊手では掘り出せない深い場所の貝まで根こそぎ採ってしまうため、貝の資源が減ってしまう原因になるのです。そのため、多くの自治体や漁業協同組合では使用を禁止しています。
また、見た目は普通の熊手に似ていても、少しでも刃が鋭かったり、網がついていたりすると「禁止道具」として扱われる場合があります。観光地などでは貸し出し用の熊手が用意されている場所も多いので、心配な場合は現地でレンタルするのが安心です。
子ども連れで行く場合も、安全面から忍者熊手は不向きです。爪が鋭いため、誤ってケガをする恐れがあります。楽しく潮干狩りをするためにも、「忍者熊手はNG」と覚えておきましょう。
どうして忍者熊手が禁止されるの?
忍者熊手が禁止される最大の理由は、自然環境と貝類の資源保護です。普通の熊手よりも掘る力が強いため、浅い場所にいる小さな貝だけでなく、深くにいる産卵前の貝や小さな稚貝までも一緒に採れてしまいます。これは、来年以降の貝の数を減らすことにつながり、潮干狩りそのものが成り立たなくなる原因になります。
また、潮干狩りスポットの多くは、地元の漁業権が設定されているエリアです。そこでは貝類の保護や管理を目的に、採っていい貝の種類や量、使用できる道具がしっかりルールとして決められています。こうした場所で忍者熊手を使うことは、そのルールを破ることになり、違反者には罰則が科されることもあります。
さらに、観光地としての価値も影響を受けます。資源が枯渇してしまえば、観光客が来なくなり、地域の収益にも大きな打撃となります。そのため、多くの地域で忍者熊手の使用は禁止されているのです。
各地で異なるルールと罰則の違い
潮干狩りのルールは、全国で一律ではなく、地域やスポットごとに細かく異なります。たとえば、千葉県の富津では、幅15cm以下の熊手しか使用できず、忍者熊手は明確に禁止されています。一方、愛知県の知多半島では、道具の種類だけでなく、採取できる貝の大きさや1人あたりの量まで厳格に制限されており、違反すると数千円〜数万円の罰金が科されることもあります。
神奈川県の横浜市では、市が発表しているガイドラインに従い、家庭用の小さな熊手のみが使用可能で、網付きや刃付きの道具はすべてNGとされています。こうした違いがあるため、事前に必ずその地域の公式サイトや観光案内をチェックすることが大切です。
「知らなかった」「見た目は普通の熊手だった」という理由では免除されない場合がほとんどなので、情報収集はしっかり行いましょう。
持ち込み禁止の道具一覧まとめ
潮干狩りで持ち込みが禁止されている代表的な道具は以下の通りです:
| 道具の名前 | 禁止理由 |
|---|---|
| 忍者熊手 | 掘削力が強すぎて資源に影響 |
| 長すぎる熊手 | 深く掘れすぎて稚貝に影響 |
| スコップ | 掘削力が強く、海底を荒らす |
| バール・金属棒 | 不自然な採取、危険性が高い |
| 大型の網袋 | 取りすぎを助長するため |
これらの道具は漁業法違反と見なされる場合があるため、絶対に使用してはいけません。安全に、かつルールを守って潮干狩りを楽しむことが、自然との共存に欠かせない姿勢です。
代わりに使えるおすすめの道具とは
では、忍者熊手の代わりにどんな道具を使えばいいのでしょうか?おすすめは以下の3つです。
- 小型の熊手
幅10~15cmのものが主流で、プラスチック製や丸い先端のものが安全です。子どもにも扱いやすいので、家族連れにも最適です。 - 手袋付きの軍手
素手で掘るとケガをしやすいので、ゴム付き軍手で貝を探る方法もあります。潮が引いた後の砂浜では意外と簡単に貝が見つかります。 - 手掘り用スコップ(おもちゃサイズ)
園芸用や砂場遊び用のプラスチック製スコップなら、安全で規制にも引っかかりにくいです。
これらの道具は観光地や潮干狩り場でレンタルされていることも多く、現地のルールに沿って楽しめます。地元のルールに合った道具選びが、楽しい潮干狩りの第一歩です。
忍者熊手が禁止される理由を徹底解説
貝の資源を守るための背景
潮干狩りで禁止されている忍者熊手。なぜこんなにも厳しく規制されているのでしょうか?
その最大の理由は、「貝の資源を守る」ためです。
忍者熊手はその構造上、普通の熊手よりも深く、広く砂を掘ることができます。これにより、表面にいるアサリだけでなく、まだ小さくて育ちきっていない稚貝や、繁殖を控えた大人の貝まで一緒に採れてしまうのです。これは、一見すると「たくさん採れてラッキー!」と感じるかもしれませんが、実際には来年、再来年の貝が育つ機会を奪うことにつながります。
貝の数が減ると、翌年以降の潮干狩りイベントが成り立たなくなりますし、地元の漁業にも大きな影響を及ぼします。自然と共生し、持続可能な楽しみ方をするためには、「必要な分だけ」「適切な方法で」貝を採ることが大切なのです。
だからこそ、道具の選び方はとても重要。たった一つの熊手が、地域の貝資源を守るか壊すかを左右することもあるのです。
地元漁業組合の立場と意見
潮干狩りスポットの多くでは、その周辺の海が「漁業権」のあるエリアに指定されています。これは、地元の漁業協同組合(漁協)がそのエリアの海産物を管理・保護するための権利です。つまり、誰でも勝手に採っていいわけではなく、漁協のルールに従って初めて潮干狩りが許可されているのです。
漁協はアサリやハマグリといった貝類の生育環境を整えるために、毎年大量の貝を放流し、環境保護活動を行っています。しかし、そんな努力も、ルールを守らない人たちの行動によって台無しにされることがあります。特に忍者熊手のような道具を使って大量に掘り起こされてしまうと、放流した貝があっという間に消えてしまいます。
漁協の方々は、「たくさんの人に楽しんでもらいたい」という思いで潮干狩り場を開放しています。だからこそ、利用する私たちもその想いに応えるように、正しい道具を使い、ルールを守ることが大切なのです。
海の環境保全に与える影響
忍者熊手は「貝を採る効率が高い」一方で、海の生態系に深刻なダメージを与える可能性があります。たとえば、熊手で砂を深く掘ると、海底のバランスが崩れます。アサリやハマグリが住んでいた場所に空洞ができたり、他の小動物が住処を失ったりするのです。
また、深く掘ることによって海水の濁りが発生しやすくなり、プランクトンの減少にもつながる恐れがあります。これは貝だけでなく、魚やカニ、エビといった多くの海の生き物の生活環境を壊してしまうことになります。
このように、忍者熊手の使用は「たくさん採れる」ことの裏に、大きな環境破壊のリスクをはらんでいます。楽しみながら自然と共生するためには、こうしたリスクをしっかり理解したうえで、行動することが求められているのです。
過去に起きたトラブルや事例紹介
実際に忍者熊手の使用によって起きたトラブルは、少なくありません。たとえば、愛知県の某潮干狩り場では、観光客がルールを無視して忍者熊手を使用し、大量の貝を採取したことで漁協とのトラブルに発展。翌年からそのエリアが閉鎖されてしまったという事例もあります。
また、関東地方でも、ルールを知らずに持ち込んだ忍者熊手が問題となり、現地の監視員に没収され、注意を受けたケースもあります。悪質と判断されれば、罰金や出入り禁止処分が下されることもあるため、トラブルを避けるためにも事前の確認が重要です。
中には「通販で買えるから大丈夫」と思ってしまう人もいますが、ネットで販売されている道具が現地で使えるとは限りません。どんなに便利でも、ルールに違反する道具は絶対に使ってはいけないという意識を持ちましょう。
「知らなかった」ではすまされない理由
潮干狩りでルール違反をしてしまった場合、たとえ「知らなかった」と言っても許されないケースがほとんどです。なぜなら、自然や漁業資源に関わる行動には重大な責任があるからです。
実際、多くの潮干狩り場では、受付時に「使用禁止道具リスト」や「ルール説明書」が配布されており、サインや同意を求められることもあります。それに従わない行為は、意図的であるかどうかに関係なく、違反と見なされます。
また、観光地によっては監視員が巡回しており、ルール違反を見つけた場合にはその場で注意されるだけでなく、道具の没収や退場、最悪の場合は警察に通報されることもあります。実際に漁業権侵害で書類送検された事例もあるため、気軽に考えてはいけません。
楽しいレジャーを台無しにしないためにも、「自分は大丈夫」ではなく、「事前に調べておく」が基本です。情報がない場合は、公式サイトや現地の案内所で確認することをおすすめします。
全国エリア別・潮干狩りルールと道具規制の違い
関東エリア(東京・神奈川・千葉など)
関東地方は、全国でも特に潮干狩りスポットが充実している地域です。特に千葉県や神奈川県では、毎年多くの家族連れや観光客が訪れます。その一方で、ルールが厳しく整備されており、道具に関する制限も細かく設定されています。
たとえば千葉県富津市の「富津海岸」では、熊手の幅は15cm以下、貝のサイズはアサリが2cm以上など明確なルールがあります。禁止されている道具の中には、刃付きの熊手や、金属製のスコップ、忍者熊手が含まれており、違反すると罰則を受ける可能性があります。
神奈川県の「海の公園」(横浜市)では、無料で潮干狩りが楽しめますが、こちらも道具制限が厳しいです。貸出用の熊手やバケツが用意されており、金属製や長さのある熊手の使用は禁止です。違反が発覚した場合は、現地スタッフから指導を受けたり、最悪の場合はその場で退場させられることもあります。
東京都内でも一部で潮干狩りが可能ですが、自然の干潟より人工干潟や河口周辺が中心です。どこでも道具や採取量の規制があるため、自治体のホームページや看板の案内を必ず確認しましょう。
関西エリア(大阪・兵庫・和歌山など)
関西エリアでは、兵庫県の「赤穂海浜公園」や、大阪府の「泉南・樽井海岸」、和歌山県の「和歌浦」などが有名な潮干狩りスポットです。これらの場所でも、道具の持ち込みには厳しいルールが設けられています。
特に兵庫県赤穂市の潮干狩り場では、漁協の管理が行き届いており、使用できる熊手のサイズや材質に明確な制限があります。金属製の鋭利な熊手や、網付きの忍者熊手は全面的に禁止されています。また、採れる貝の種類もアサリなどに限られており、シジミやハマグリなどを採取するには許可が必要な場合もあります。
大阪府泉南地域では、イベント形式の潮干狩りが開催されることが多く、貸出用の道具のみで楽しむスタイルが主流です。つまり、マイ熊手持参不可というケースもあるので、事前に公式サイトを確認する必要があります。
和歌山県では自然の干潟を楽しめる場所もありますが、近年は資源保護のため一部エリアでの採取が制限されていたり、事前申請が必要になっていたりします。禁止道具の使用はルール違反とみなされ、発覚すれば没収・注意だけでなく、罰金が課せられることもあります。
東海エリア(愛知・三重・静岡など)
東海エリアは日本でも屈指の潮干狩り天国です。特に愛知県の「知多半島」や三重県の「伊勢湾沿い」、静岡県の「浜名湖」などは、毎年多くの観光客が訪れます。それに伴って、ルールも非常に細かく、違反に対する監視も厳しい地域です。
愛知県の知多半島では、漁業権が強く保護されており、潮干狩り場では明確な道具規制があります。幅15cm以上の熊手、刃付き熊手、そしてもちろん忍者熊手は全面的に禁止です。また、1人が採取できる貝の量にも制限があり、超過するとその場で罰金を請求されることもあります。
三重県では観光型潮干狩り場が多く、基本的に入場料を払って指定されたエリアで楽しむスタイルが一般的です。ここでも道具はレンタルが基本で、持ち込み道具には厳しい制限があります。スタッフの指示に従い、安全でルールを守った潮干狩りが推奨されています。
静岡県の浜名湖や焼津市周辺では、潮干狩り解禁期間が設定されており、それ以外の時期は原則禁止となっています。しかも、解禁されていても道具の種類、貝のサイズ、量などの細かいルールが決められており、違反すると漁業権侵害とされてしまいます。
九州エリア(福岡・長崎・熊本など)
九州でも潮干狩りは盛んで、福岡の「和白干潟」や、熊本の「荒尾干潟」、長崎県の「諫早湾干拓地」などが有名です。いずれも豊かな自然を残しつつ、地元のルールに従って潮干狩りを楽しめるよう整備されています。
福岡県の和白干潟では、都市近郊にも関わらず自然環境がよく保たれており、アサリやマテガイが豊富です。ただし、漁協が管理しているため、忍者熊手や金属製の大型熊手は禁止されています。また、ここでは環境保全活動も活発に行われており、マナー違反に対しては地域住民からの注意が入ることも。
長崎県では観光用に整備された潮干狩りスポットがいくつかあり、無料で利用できる場所と有料エリアがあります。いずれも道具に関しては自治体や地元漁協のガイドラインに従う必要があります。熊手の材質やサイズについて確認しておきましょう。
熊本県の荒尾干潟では、自然保護の観点から「採取禁止エリア」も多くあります。場所によっては事前申請や許可証が必要なケースもあるので、しっかり下調べが大切です。
北海道・東北・中国・四国エリア
北海道や東北では、気候や潮の満ち引きの関係で、潮干狩りができる場所はやや少なめですが、それでも一部地域では楽しめるスポットがあります。北海道では厚岸や函館周辺、東北では青森の十三湖などが知られています。
これらの地域では、潮干狩りが可能な期間が短く、解禁されている時期も限られています。そのため、許可制や指定エリアでの実施が多く、道具の規制も厳しめです。漁協や市町村によって決められているルールをしっかり確認してから出かけましょう。
中国地方では、島根県や広島県の干潟が有名で、四国でも徳島県の鳴門や香川県の坂出などで潮干狩りができます。これらのエリアでも、忍者熊手の使用は禁止されているのが一般的です。また、四国では一部のスポットで予約制を採用しており、ルール説明を事前に受ける必要があることもあります。
全国どこであっても、「ルールを知らなかった」では済まされません。楽しい思い出を作るためにも、事前の情報確認は欠かせません。
潮干狩りを楽しむためのマナー集
ごみは持ち帰るが基本中の基本
潮干狩りに限らず、自然の中で遊ぶときの基本的なマナーが「ごみは持ち帰る」ことです。潮干狩り場には、砂浜に貝殻や食べ物の包装紙、使い捨てのプラスチック容器などがそのまま放置されてしまうケースがあります。しかし、これらは自然に分解されるまで何十年もかかるものもあり、海の生き物にとって大きな害になります。
特に子ども連れで行く場合、「来たときよりもきれいにして帰ろう」というルールを家族で共有することはとても大切です。簡単なビニール袋やエコバッグを持参すれば、ごみの持ち帰りは難しくありません。
また、一部の潮干狩り場ではごみ箱の設置がない場合もあります。観光客の増加とともに、ごみ処理の問題が深刻化しているため、主催者側も「持ち帰り」を前提とした案内をすることが増えています。
環境保護は難しいことではありません。ほんの少しの気づかいが、次に来る人のため、そして自然を守るための大きな一歩になります。
他人のエリアに勝手に入らない
潮干狩り場では、場所取りがある程度自由な場合が多いですが、すでに誰かが用意していたり掘っていたエリアに無断で入り込むのはマナー違反です。中には「ここに貝がいるから」と他人の近くに寄っていく人もいますが、それではトラブルの元になります。
特に有料の潮干狩り場や指定エリア制の場所では、場所の区分けがしっかりされています。テープやロープ、旗などで仕切られている場合には、そのエリアを無断で使うと主催者や他の利用者に迷惑がかかることになります。
「潮が引いてるからどこでも大丈夫」と思わずに、他の人との距離感や使用範囲をしっかり守りましょう。狭いスペースでのトラブルはお互いにとって嫌な思い出になってしまいます。
潮干狩りは、自然の中でみんなが楽しむもの。お互いが気持ちよく過ごすためには、場所のマナーをしっかり意識することが重要です。
一人で大量に採らない配慮
潮干狩りに夢中になると、ついついたくさんの貝を採ってしまいたくなりますが、採りすぎはNGです。ほとんどの潮干狩り場では「1人あたりの持ち帰り量」が決められています。たとえば、1人2kgまで、アサリは1人100個までなど、ルールが定められている場所が多いです。
このルールは、自然の資源を守るためだけでなく、他の利用者とも公平に楽しむためのものです。ある人が大量に採ってしまうと、他の人が貝を見つけられなくなってしまい、せっかく来たのに何も採れなかった…ということも起こり得ます。
また、大量に採っても、実際には食べきれなかったり、腐らせてしまうこともあります。せっかく自然からもらった恵みですから、必要な分だけ、ありがたく持ち帰るという意識が大切です。
「自分さえ良ければいい」ではなく、「みんなが楽しめるように」の気持ちで潮干狩りをすることが、良いマナーといえるでしょう。
子ども連れで気をつけたいこと
潮干狩りは子どもにとっても自然と触れ合う絶好の機会ですが、保護者として注意すべきポイントがいくつかあります。まず一つ目は、安全確保。潮の流れや砂のくぼみ、ぬかるみに注意が必要です。特に干潮から満潮にかけての時間帯は、急に水かさが増えてしまうことがあるので、必ず時間をチェックして行動しましょう。
また、道具の取り扱いにも注意です。金属製の熊手やスコップは小さな子どもには危険です。できればプラスチック製のおもちゃ道具や、素手でも掘れるような柔らかい砂の場所を選ぶのがおすすめです。
さらに、長時間日差しの中にいることになるため、帽子や日焼け止め、水分補給は必須です。こまめに休憩をとることも大切です。
最後に、採った貝は必ず親がチェックを。小さすぎる貝や死んでいる貝を持ち帰ると、食中毒などのリスクもあるため注意が必要です。
子どもにとって楽しい思い出になるように、大人がしっかりサポートしましょう。
SNS投稿前に確認したいこと
潮干狩りの風景や、たくさんの貝を採った様子をSNSに投稿する人も多いですが、投稿する前に少しだけ注意したいポイントがあります。
まず一つ目は、場所の特定。マイナーな潮干狩りスポットや、地元の人しか知らないような穴場を写真付きで紹介すると、次回以降に人が殺到してしまい、地元住民とのトラブルに発展することがあります。場所の情報は必要最低限にとどめた方がいいでしょう。
次に注意したいのが、採取量や道具の見せ方です。法律違反となるような量の貝や、禁止されている道具(たとえば忍者熊手など)が写っていると、それだけで批判を浴びたり、通報されることもあります。
また、他の利用者が写っている写真や、子どもの顔がはっきり写っている写真を無断でアップすると、肖像権の問題になる場合もあります。マナーとして、プライバシーに配慮した写真選びや加工を心がけましょう。
SNSは楽しい思い出をシェアする素敵な場所ですが、「見せ方一つ」で評価が大きく変わります。他人に不快な思いをさせない投稿を心がけましょう。
これからの潮干狩りに必要な心得
ルールを知ることが安全の第一歩
潮干狩りは自然の中で楽しめるレジャーですが、「自然相手」だからこそ、ルールを知らないまま参加すると思わぬトラブルや危険に巻き込まれることがあります。まず大切なのは、「その場所のルールを事前に調べること」です。
同じ県内であっても、漁協や市町村ごとにルールが異なることが多く、使える道具、採れる貝の種類、量、サイズ、解禁期間などが細かく設定されています。「去年行ったときは大丈夫だったから今年もOK」とは限らないので、毎年最新情報を確認する習慣をつけましょう。
また、安全面のルールも重要です。たとえば、満潮時刻のチェックや、天気・風の状況、子ども連れの場合の注意点など、下調べは多ければ多いほど安心です。
ルールを知って守ることで、自分も周りも気持ちよく過ごせるのが潮干狩りの魅力です。楽しい思い出を台無しにしないよう、事前準備とマナーの確認を忘れないようにしましょう。
楽しみながら自然を守る方法
潮干狩りはただのレジャーではなく、自然と人が直接ふれ合える貴重な体験です。だからこそ、「楽しみながら自然を守る」という意識を持つことがとても大切です。
具体的には、貝の採りすぎを避けること、小さな稚貝は元に戻すこと、使った道具や持ち込んだものはすべて持ち帰ることなど、ひとつひとつの行動が自然保護につながります。もし時間に余裕があれば、拾ったごみを持ち帰る「ついで清掃」も素敵な取り組みです。
また、子どもたちに自然の大切さを教える機会にもなります。「生き物を大切にする」「自然は限りあるもの」などの考え方を、実体験を通して学べるのが潮干狩りの良さでもあります。
自然を壊してまで楽しむのではなく、自然と共に楽しむ。そんな姿勢が、これからの潮干狩りには求められています。
地元の人との共存を意識しよう
潮干狩りスポットは観光地であると同時に、地元の人たちの生活の一部でもあります。アサリやハマグリなどの貝は、漁業収入の一部であり、地域にとって大切な資源です。
だからこそ、訪れる側としては「おじゃまする」という気持ちを忘れないことが大切です。近隣の駐車場やトイレの使い方、路上駐車の問題、騒音やごみの放置など、観光マナーが悪いと地域との信頼関係が壊れてしまいます。
地元のルールに従い、指示された場所で道具を使い、施設をきれいに使う。当たり前のことですが、それを丁寧に守るだけで、地域の人との良好な関係を築くことができます。
潮干狩りは、その土地に暮らす人たちの協力があってこそ実現しています。共存の意識を持って訪れましょう。
道具選びで気をつけるポイント
潮干狩りの道具選びで特に注意したいのが、「使用可能な道具かどうか」を事前に確認することです。ネットやホームセンターで売っている熊手の中には、ルール違反とされるものも含まれており、買ったからといって必ずしも使っていいわけではありません。
ポイントは以下の通りです:
- 幅は15cm以内
- 刃や金属の尖った部分がない
- 網付きでない
- 柄が極端に長くない
また、持ち込む前に「現地でレンタル可能かどうか」も調べておきましょう。最近は、潮干狩り場で道具をレンタルしているところも多く、安全でルールに合った道具が使えるため安心です。
誤った道具を持ち込むと、注意を受けるだけでなく、没収や退場のリスクもあります。せっかくのレジャーを楽しく終えるためにも、道具選びは慎重に行いましょう。
次世代に残すためにできること
私たちが潮干狩りを楽しめるのは、過去から受け継がれてきた自然と、守り続けてきた人たちのおかげです。そして、これからも同じように潮干狩りを楽しむためには、「次の世代に自然と文化を引き継ぐ意識」が必要です。
子どもたちに正しいマナーやルールを教えることは、その第一歩です。「ただ遊ぶ」だけでなく、「なぜルールがあるのか」「自然はどうやって守られているのか」を伝えることは、未来の環境保護にもつながります。
また、SNSでの発信や口コミを通じて、正しい情報やマナーを広めることも大切です。自分の行動が誰かの手本になるという意識を持ちましょう。
潮干狩りは、ただのレジャーではなく、自然とのつながりを感じる大切な文化です。私たち一人ひとりができることを少しずつ積み重ねて、次の世代にその楽しさと豊かさを伝えていきましょう。
まとめ
潮干狩りは、自然とふれあいながら家族や友人と楽しい時間を過ごせる日本ならではのレジャーです。しかし、その楽しさの裏には「自然資源の保護」や「地域のルールへの理解」といった、大切な配慮が必要です。
特に問題視されている「忍者熊手」の使用は、貝の資源を減らし、海の環境を壊してしまうリスクがあります。便利だからと使ってしまうのではなく、「なぜ禁止されているのか」を理解し、正しい道具を選ぶことが重要です。
また、地域ごとに異なるルールを守ることや、他の利用者、地元の人たちへの配慮も忘れてはいけません。ごみを持ち帰る、採りすぎない、SNSでの配慮など、小さな行動が自然と人とのつながりを守ることになります。
潮干狩りを通じて学べることは、単に貝を採ることだけではなく、「自然との共存」や「持続可能な楽しみ方」です。今後も楽しく、安全に、そして未来の世代へとこの素晴らしい文化を引き継いでいけるよう、一人ひとりが意識をもって行動しましょう。